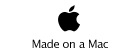序

バッハは音楽家である前に、資本主義勃興前夜の近代ドイツに生きた生活人であり、自立した思想を持つ知識人であった。彼は独自のイエス観と神への信仰を持ったクリスチャンではあったが、本論で明らかになるように、その信仰は、当時のドイツ社会で正統とされるものではなかった。それを強く示唆する事件も、実際に起こっている。1739年3月にバッハに通告された受難曲演奏禁止の処分である。詳しくは本論を読んでいただくとして、これまでの研究者による種々のバッハ論はそれをバッハの頑迷な性格か、行き違いによって起こったささいなエピソードとしてしか扱っていない。これまでのバッハ論は大きく分けて二つのグループに分かれる。一方はバッハを「敬虔なクリスチャンとして、一生を神への音楽に捧げた」とし、他方は「バッハの音楽の基本は世俗曲、器楽曲にあり、宗教曲は要請に応じて義務的に作ったパロディに過ぎない」とするものである。しかし、どちらの結論も、客観的な総合的研究に基づいているというより、そうであってほしい願望を反映して、一部の資料で全体を判断しているとしか思えない。それでは、永遠に交わることのない、すれ違いの議論になるしかない。それらの典型的な例は、一方は数象徴論であり、多くは彼の宗教曲で特定の楽章に使われた小節や音符の数に聖書の章や節の数を当てはめて解釈する。他方は、例えば最晩年に書かれた《ロ短調ミサ曲》について、ルター派教会の音楽監督であることに辟易したバッハが、自由を得るために通作ミサ曲を書くことでカトリック系のドレスデン宮殿に猟官運動を行ったとするものである。他の証拠によって裏付けられていないかぎり、これらの議論に科学的根拠を見いだす事はできない。議論は噛み合ず、お互いに言いっぱなしになるだけである。数象徴を言えば、研究者が好きなように「数」を解釈して、キリスト教とも無関係なとんでもないバッハ像さえメイクアップできるし、他方ではバッハをヘンデルのようにスノビッシュな出世主義者と貶めることも可能である。それらは、キリスト教神学や、ドイツの宗教改革に詳しくないバッハファンを、いわば煙に巻くような議論にすぎず、実証的研究によって得られた再現性のある結論とはいえない。そのような似非科学に惑わされないためにも、キリスト教の歴史について多少の知識を持っていることが望ましい。
バッハのイエス観については、本論で明らかにして行くが、初期キリスト教の歴史に通じていない多くの日本人読者のためには、予備知識として初期キリスト教について簡単に触れておくことは無駄ではないだろう。とりわけ多くの日本人は、初期キリスト教はいわば暗闇の中にあって、バッハとの関わりはない大昔の話であると思っているかもしれない。しかし、バッハ自身がその時代に興味を持っていたことは、蔵書の遺産目録からも伺える (注1)。ローマ帝国によって国教化されるまえの初期キリスト教の時代には、イエスを聖人として神の下位におくアリウス派が長く優勢であった。特に現在のギリシャ、シリア、トルコ、エジプトなどではそうであった。そのころは、キリスト教徒は社会的少数派であり、弾圧される側であった。そのような弱者であったキリスト教徒が内部抗争をする余裕は無く、もっぱら社会に対して防衛的で、内部ではお互いの自由な信仰を許容していた。しかし、西方に逃れて、ローマに拠点を移した西方教会派は、「父と子と聖霊」の三位一体説を唱えて次第に勢力を伸ばし、前者を異端として激しく攻撃するようになる。あたかも、時はコンスタンチヌス1世(在位:306 -337)が、東と西に分裂していたローマ帝国を統一し、独裁的権力を確立したころである。西方教会は積極的に世俗権力に取り入る工作を始めてそれを次々と成功させる。コンスタンチヌス1世は死の直前までキリスト教徒ではなかったが、キリスト教を合法化して国教化への道を開き、聖ピエトロ寺院を創建し、第1ニケーア公会議で アリウス派を異端とし、三位一体説を正統とする決定をした。以上のことから、イエスの神格化が完成するには、死後数百年も必要だったことがわかる。しかし、ローマ帝国で国教化された正統派(カトリック)は、優遇税制を得るなど政治的にも、経済的にも強い社会基盤を確立し、世俗権力への影響力を強め、やがてローマ帝国の実質的な支配者となり、ローマ帝国の崩壊後も各国の王位任命権をにぎるようになる。しかし、14世紀になると内部からの腐敗が顕著になり、イングランドのジョン・ウィクリフやボヘミアのヤン・フスに始まる宗教改革の運動がヨーロッパに広がる。ドイツでは、16世紀になって、信仰は聖書にのみ基づくと信仰の自由を唱えたマルチン・ルターは、ギリシャ語正本(当時はエラスムス版)からラテン語にしか翻訳が許されていなかった聖書をドイツ語に翻訳し、農民や庶民にも読めるようにする。そして、ルターの生前最後に出版されたルター訳聖書が決定版(1545)となり、その後の改訂版も含めて広く庶民に普及していく。しかし、ルター自身はマキャベリストであり、政治的宗教家でもあった。彼が始めたドイツプロテスタント(ルター派)は、カトリック勢力との苛烈な戦いに勝利するために、しだいに世俗権力に取り入るべく方向転換を行う。農民戦争ではルターを慕う庶民を裏切り、農民を殺戮する諸侯に取り入る選択をする。そのためにルター派は、ほとんどの基本的な思想をカトリックから引き継ぐことになり、果てはカトリックと同じか、それ以上に血なまぐさい宗派となる。それらの思想には三位一体説だけでなく、反ユダヤ思想、魔女裁判などの異端審問も含まれている。当初は、信仰は聖書のみに基づくとして、自由な信仰を求めたルターも、異端との戦いは敬虔な信仰者の重要な責務と主張するようになる。バッハの教会音楽も、ライプチッヒ初期までは、ルター主義正統派の戦闘主義的思想を色濃く反映しており、カトリック、反福音主義、再洗礼派、イスラム教などの異端との戦いを煽るカンタータが含まれている(注2)。彼の教会音楽からこのような、戦闘的ルター主義の影が見られなくなるのは、《マタイ受難曲》成立(1729)のころからである(注3)。バッハの個人史では、バッハと聖トーマス教会聖職会議、ライプチッヒ市参事会とが激しく対立したあとの時期にあたり、翌年の8月には職務怠慢を理由にバッハは減俸処分を受ける。これが《マタイ受難曲》初演時の悪評と関わりがあった可能性もあるが、根底には初めからバッハの中に秘められていたある確信 ─ 信仰における音楽の役割についての ─ との衝突があった。おそらく、バッハの思想はライプチッヒ前から萌芽的に形成されていたが、ライプチッヒ初期においては自分の能力を低く見たライプチッヒ市上層部に待遇改善を訴えるため、思想的主張よりも音楽能力を認めさせるほうを優先させたのであろう。子沢山で、息子達の大学進学にこだわっていたバッハにすれば、給与や収入を優先させたとしても無理からぬことである。しかし、それが功を奏さないまま、1728年9月に決定的なことが起こった。聖職会議が、礼拝式に用いるコラール選定権をバッハから奪うという通告を出したのである。それは、バッハにとっては、自分の信仰と信念が否定されたに近い決定的な意味を持っていた。もはや、ライプチッヒ市と教会には何も期待できないと思ったに違いない。その後、彼がカトリック系のドレスデン宮殿に近づこうとしたのは確かだが、そのかいもなく、名目的な処遇の改善があっただけで、彼の望む収入の改善にはつながらなかったし、その後も自分の考える宗教音楽が認められる機会すらなくなっていった。
1729年初演の《マタイ受難曲》を、1733年に一部改訂、変更して完成させる。そのなかで、バッハは教会批判の思想をより鮮明に書き込む。その完成稿は、バッハが実際に演奏に使ったと理解されているが、すくなくともそのままの形で演奏することは不可能に近いものだった。もしそれが実際に浄書譜のとおりに演奏されたのなら、受難曲演奏禁止処分が下されるのも必然であった。実際に、受難曲演奏禁止が通告されたときにバッハは歌詞が問題とされた可能性を示唆する反論をしている(注4)。バッハが《マタイ受難曲》に書き込んだ思想には、当時のカトリックとも、プロテスタントとも相容れない東洋的なものを私は感じる。それが、バッハ自身と彼の一族が信じていたように、バッハ家の出自が、ドイツではなくアジアに起源があるハンガリー系であったことと関係あるのかどうかは、私にはわからない。しかし、その思想は日本で言えば法然や親鸞に代表される浄土思想、悪人正機の思想に近いものだった。
(注1) バッハの蔵書のなかに、ユダヤ教を捨て、ローマ帝国に寝返ったとされるユダヤ人歴史家であるフラウィウス・ヨゼフスがAD90年ころに完成させた「ユダヤ史」があったことが分かっている。彼はイエスと同時代に生きた人物である。ヨゼフスについてのバッハの考えはのこされていないが、書籍が高価であった当時であればバッハが実在のイエスとその後の時代に興味を持っていたことは確実である。
(注2) BWV18(1713年)、BWV19(1726年)、BWV126(1725年)など。
(注3) 通説では1727年初演が信じられているが、筆者は1729年初演のほうが可能性は高いと思っている。詳しくは本文で触れるが、本論の結論とは直接の関係はない。
(注4)一般にこの処分は《ヨハネ受難曲》に対して出されたものと推定されているが、筆者は《マタイ受難曲》に対して出されたものであると推定する。